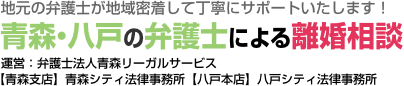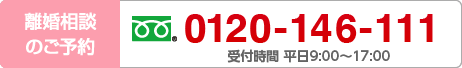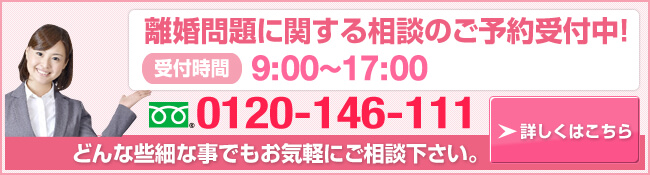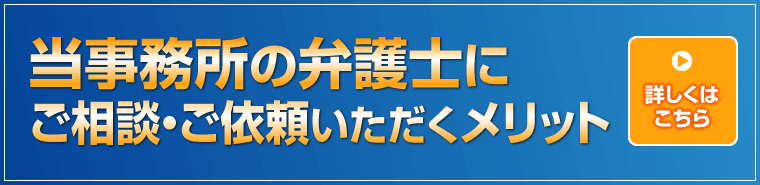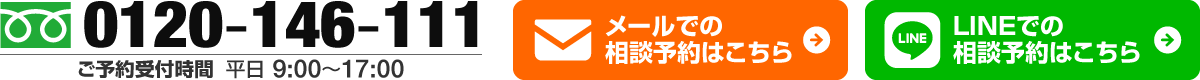配偶者と離婚したいと考える場合、それぞれのご事情はあると存じますが、「一刻も早く離婚したい」「とにかく離婚したい」という衝動にかられる方もいらっしゃるかもしれません。
もっとも、離婚に向けた準備をせずに離婚を切り出してしまうのは、リスクが非常に大きいです。
そこで、この記事では、事前の準備なく離婚を切り出すことのリスクや、離婚に向けて事前に準備すべきこと、離婚を切り出すタイミングといった事項を中心にご説明させていただきます。
1 事前準備なく離婚を切り出すリスク
(1)適正な条件で離婚できなくなる可能性がある
離婚をする際は、一般的にお互いが結婚期間中に築き上げた財産について、公平に分けることがあります(財産分与)。
もっとも、事前準備なく離婚を切り出してしまうと、その後、配偶者名義となっている預貯金や株式などの財産として何があるのか、資産価値としてどの程度あるのか、ということを把握することが困難になってしまうことが想定されます。
財産分与で分けるべき財産について把握できず、財産分与の対象から除かれたまま財産分与を行った場合、その離婚条件は適正な内容とはいえず、不利な内容で離婚することとなります。
また、あなたが配偶者と離婚したい理由として、配偶者が不貞しているなど、配偶者に対して慰謝料請求をできる場合もあります。
もっとも、これに関する証拠を確保しないままに離婚を切り出してしまうと、配偶者が慰謝料の発生根拠を否定してきたような場合に、こちらが慰謝料を請求する権利があることを証拠とともに示すことができないこととなります。
最終的に配偶者が慰謝料の支払を拒むような場合には、裁判所の手続を利用することを検討することとなりますが、その際、証拠が手元にない場合には、こちらの慰謝料請求は認められず、結局、泣き寝入りになってしまいかねません。
そのため、事前準備なしに離婚を切り出した場合には、適正な条件で離婚することができなくなる可能性があります。
(2)離婚(別居)後の生活に困窮してしまう可能性がある
何も準備することなく離婚を切り出すということは、離婚後、あるいは離婚を前提とした別居をした後、どこに住み、どのような収支のもとで生活するのか、その生活をするにあたって必要な初期費用はどのくらいなのか、といった計画を立てていないということを意味します。
このような場合、いざ離婚(別居)した後の収支のバランスが取れず、生活に困窮してしまう可能性があります。
(3)話し合いが進展せず、長期化してしまう可能性がある
離婚というのは、生活状況・人間関係が一変する大きな出来事ですので、あなたが配偶者に対して離婚を切り出した際、配偶者がすぐに離婚に応じてくれるという甘い期待は持つべきではありません。
あなたが離婚を考えている理由をうまく説明することができない状況や、今後のライフプランを持てていない状況、その他、離婚の条件についての具体的な考えを持っていない状況で離婚を切り出した場合、離婚すること自体や、離婚条件についての話し合いがスムーズに進まないことが想定されます。
そのため、事前準備をすることなく離婚を切り出した場合には、話し合いは進展せず、離婚への話し合いが長期化してしまう可能性があるといえるでしょう。
2 離婚に向けて事前に準備すべきこと5選
離婚に向けて事前に準備すべきことを5つに絞ると、次に挙げたものが大切です。
①心の準備をしておく
②離婚したい理由について整理しておく
③生活面での独立の準備をする
④証拠の収集をする
⑤離婚の条件等に関する方針を決める
以下、それぞれについて、詳しくご説明させていただきます。
(1)①心の準備をしておく
上記のとおり、離婚は、生活状況・人間関係が一変する大きな出来事です。
離婚することによって、配偶者と同じ空間で生活する必要がなくなるため、その言動に対する精神的なストレスがなくなることや、生活面や経済面の面倒を見なくてよくなることは、大きなメリットと考えられます。
他方で、離婚することにより、家事、育児、仕事など、夫婦で協力して行っていたものについて、その全部ないし一部をひとりで背負うこととなる可能性があります。
その他、家庭の事情というのは様々であるため、各家庭において考慮しなければならないことがあるでしょう。
そのため、こういった様々な事情を考慮したうえで、自分の中で離婚したいという意思が固いかは考えておく必要があるでしょう。
また、離婚する際や離婚した後、様々な物事に関して、あなた自身が決断し、行動しなければなりません。
そのため、精神的に配偶者から独立しなければならないということを、第一に頭に置いておく必要があるといえるでしょう。
(2)②離婚したい理由について整理しておく
あなたが配偶者と離婚したいという意思が固い場合、離婚したい理由を整理しておくのが良いでしょう。
あなたの気持ちとして、離婚したいという理由が明確になっており、気持ちが整理されている場合には、配偶者に対して離婚を切り出したタイミングや、離婚に関する話し合いをした際に、あなたの考えていることを冷静に配偶者に伝えるのに役に立つこととなります。
もっとも、配偶者には配偶者の言い分があることも想定されます。
そのため、あなたの気持ちとして離婚したい理由が整理されているからといって、配偶者がその理由を納得してくれるとまでは考えない方がよいでしょう。
配偶者が離婚に応じない場合には、調停手続などの裁判所の手続を利用する必要があります。
調停手続で配偶者が離婚に合意してくれない場合には、離婚訴訟によらなければ離婚することができません。
そして、離婚訴訟では、法律で定められている離婚原因がなければ離婚はできません。
配偶者が頑なに離婚に応じてくれないことが想定される場合には、法律で定められている離婚原因に当てはまるか、確認しておくと良いでしょう。
【関連ページ】
●法律で定められている離婚原因
(3)③生活面での独立の準備をする
離婚後はもちろんのこと、離婚を切り出した後、話し合いが進まないような場合も同居し続けるのか、それとも、別居をして生活するのか、という計画を立てる必要があります。
具体的には、住む場所や別居後の収支、別居する際の初期費用(引っ越し代、最低限そろえる必要がある家具・家電、賃貸物件の初期費用等)に関して試算し、見通しを立て、生活面で困ることがなく、独立して生活していくことができるよう、準備をしておく必要があります。
なお、双方の収入状況等によっては、別居後、離婚までの期間、配偶者に対して婚姻費用を請求することができます。
また、離婚後、あなたが子どもの親権を持つ場合には、(元)配偶者に対して養育費を請求することができます。
もっとも、婚姻費用や養育費の金額に関して(元)配偶者との間で合意できない間は、配偶者から婚姻費用や養育費が支払われないリスクがあります。
そのため、相手方からの婚姻費用や養育費が支払われないリスクも考慮したうえで、準備する必要があります。
(4)④証拠の収集をする
配偶者に対して離婚したいことを切り出しても、離婚自体を拒否してきたり、その条件面で合意することができなかったりすることにより、スムーズに離婚できない可能性があります。
このような場合に、配偶者との間で、適正な内容で離婚するためには、その証拠が欠かせません。
そのため、事前に以下のような証拠については、可能な限りでそのコピーなどを収集しておくのがよいでしょう。
〇婚姻費用や養育費に関係する資料
・所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書類、給与明細など)
〇財産分与に関係する資料
・預貯金通帳
・生命保険が記載された書類
・不動産登記簿
・証券口座に関する明細
〇慰謝料に関係する資料
・不倫に関係する資料(メールやSNS、写真、録音など)
・DVに関係する資料(診断書、あざや傷の写真、DVに関するSNSのやりとり、日記など)
(5)⑤離婚の条件等に関する方針を決める
④で集めた証拠も考慮して、おおむね以下の内容について、どのような条件で離婚するのか、その方針を考えておく必要があります。
〇親権
未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権者を決めなければ離婚することができません。
子どもの親権者を決めるにあたっては、子どもの利益を最優先に考え、決める必要があります。
これまでの監護状況や、双方の監護能力、離婚後の監護環境などの事情も考慮して、どちらが親権者となるべきか、しっかりと考えておく必要があるでしょう。
〇養育費
子どもが健全に発育・生活していくためには、養育費は欠かせません。
お互いの収入状況等に照らして、適切な養育費の金額、養育費を支払う期間、その他、特別な支出が発生する場合の負担などについて決める必要があります。
〇面会交流
仮に夫婦が離婚したとしても、子どもにとってそれぞれが親であることは変わりません。
面会をすることによって、子どもの健全な発育が阻害されるといった例外的な場合を除いて、子どもの健全な発育のためには、面会交流を実施することを検討する必要があります。
面会交流に関する取り決めをするにあたっては、その頻度や方法、その他の決まりごとをどのようにするか考えておく必要があるでしょう。
〇財産分与
婚姻期間中、夫婦の協力によって築いた財産は、離婚の際に、2分の1ずつに分割することとなります。
仮に、あなたが専業主婦(主夫)だったとしても、家事や育児によって配偶者を支え、財産の形成に貢献していると考えられるため、財産分与を受けることができます。
ただし、それぞれが婚姻前から持っていた預貯金や、相続によって得た財産など、夫婦の協力によって築いた財産とは評価されないものについては、財産分与の対象外であるため、この点は注意する必要があるといえるでしょう。
〇慰謝料
慰謝料は、離婚する場合に常に発生するものではありません。
配偶者に不貞行為があった場合や、DVがあった場合など慰謝料が発生するような出来事があった場合に限定されます。
慰謝料を請求するにあたっては、配偶者がその事実関係や金額等について争ってくることが多いので、上記の④に記載したとおり、その証拠が非常に大切になってきます。
〇年金分割
婚姻期間中に夫婦の双方または一方が納付していた厚生年金保険料は、夫婦が互いに協力していたことにより納付されたと考えられることから、お互いにおいて積み立てていた厚生年金保険料の差額について、基本的に2分の1の割合で按分したものを受領することができます。
ただし、離婚時に現金で受領できるのではなく、老後に受領できる年金の額に加算されることになりますので、この点は誤解しないように気をつけていただければと思います。
〇婚姻費用
夫婦は、法律上婚姻関係にある期間中は、お互いに助け合い生活する義務を負っています。
そのため、別居した後、離婚するまでの期間など、家族が別々の生活拠点で生活しているような場合に、お互いの収入状況に照らして、配偶者に対して生活費を請求できる場合があります。
婚姻費用は、養育費と異なり、離婚後ではなく、離婚までに発生するものですが、離婚を切り出した場合には、その後、話し合いによっては別居するということも想定されるため、考えておく必要があります。
3 離婚を切り出すタイミング
仮に、配偶者からDVの被害を受けているような場合や、子どもが虐待を受けている場合のような緊急事態であれば、準備が十分に整っていなくても、まずはその場から抜け出し、物理的距離を置き、ご自身や子どもの心身の安全を確保することを最優先に行動してください。
心身の安全を確保したうえで、可能な限りで証拠の収集をすればよいでしょう。
他方で、上記のような緊急事態にない場合、まずは準備すべきものの準備をしっかり進めていくのが良いでしょう。
そして、準備が十分に整った段階で、離婚を切り出すべきです。
離婚を切り出すシチュエーションとしては、お互いに飲酒などしておらず、冷静に話し合いができるタイミングを見計らい、離婚を切り出すべきです。
離婚の話という性質上、配偶者が感情的になりやすいのですが、こちらも感情的になってしまうと話し合いが進まなくなってしまう可能性があるため、こちらは冷静に話をしていくのがよいでしょう。
4 離婚でお悩みの方は当事務所にご相談ください
それぞれのご家庭によって、抱えている悩みや、離婚に向けてできる準備の内容・やるべき準備の内容は異なります。
家庭の状況や、具体的なお悩みをお話しいただければ、当事務所の弁護士が、あなたのお悩みに対して直接アドバイスすることができます。
離婚に関してお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
(弁護士・畠山賢次)