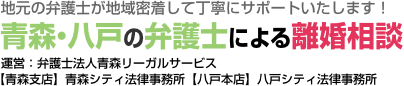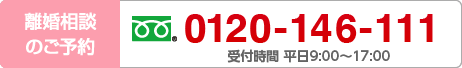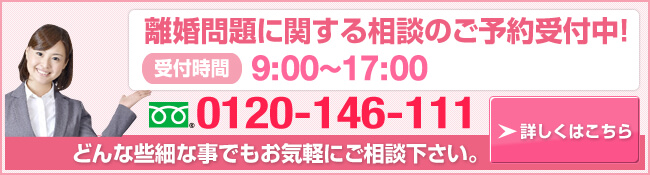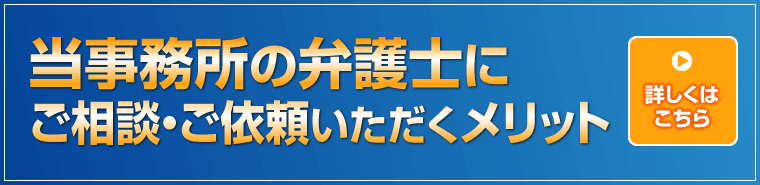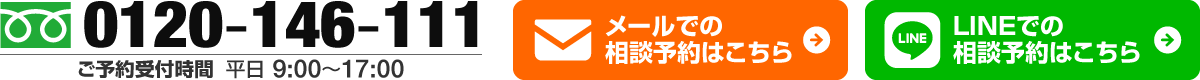1 共同親権とは?
(1)親権とは

親権とは、子の監護及び教育に関する親の権利であり、義務でもあります。
その具体的内容としては、以下のように整理されます。
①身上監護権
・居所の指定
・職業の許可
・身分上の行為の代理
・その他子の養育に必要な各種行為
②財産管理権
・財産の管理
・財産に関する行為の代理
(2)現行法における単独親権
現行法においては、離婚の際、父母のいずれか一方を未成年の子の親権者と定めるものとされています。
そして、離婚後は、親権の内容である身上監護権や財産管理権について、親権者がすべて単独で行使することとなり、親権者とならなかった側にはこれらに対する権限がありません。
そのため、親権者とならなかった側は、養育費や面会交流といった限度でしか子に関与できず、具体的な監護・養育については親権者のみに委ねられる形になります。
(3)共同親権とは
共同親権とは、法改正によって創設された、離婚時に、父母の両方を親権者にするという新たな選択肢です。
これにより、同居親だけではなく別居親も親権者となり、上記のような親権の行使に関与していくことが可能となります。
2 共同親権の開始時期は?
共同親権について定める改正民法は、令和6年(2024年)5月17日に成立し、同月24日に公布されました。
施行時期は公布の日から2年を超えない範囲で政令により定めるものとされましたので、令和8年(2026年)5月までには共同親権が開始することになります。
3 共同親権で何が変わる?
共同親権を選択した場合、子の監護・養育に関する事項を親権者両方で決定していくことになります。
とはいえ、日常的なことにまで常に親権者間で協議して決定することは困難であり、監護及び教育に関する日常の行為については単独で行使できるものとされました(改正民法824条の2第2項)。
そのため、日常的なことは同居親限りで決定しつつ、子にとっての重要な事項については親権者両方で決定することになっていくと思われます。
なお、どこまでが日常の行為にあたるかについては、法務省作成の資料において、以下の例が挙げられています。
〇日常の行為に当たる例
・食事や服装の決定
・短期間の観光目的での旅行
・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
・通常のワクチンの接種
・習い事
・高校生の放課後のアルバイトの許可
〇日常の行為に当たらない例
・子の転居
・進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)
・心身に重大な影響を与える医療行為の決定
・財産の管理(預金口座開設など)
そして、親権者両方で決定する事項について、協議が整わないときで、かつ、子の利益のために必要があるときは、家庭裁判所が、当該事項に関する親権をいずれかが単独で行使できる旨を定めることになります(改正民法824条の2第3項)。
そのほか、一方の親権者が親権を行うことができないときや、子の利益のため急迫の事情があるときも、一方の親権者のみで親権を行使できるものとされています(改正民法824条の2第1項)。
4 共同親権のメリットを解説
(1)別居親が子にとって重要な決定に関与できる
別居親からすると、子の転居や進学といった重要事項の決定に関与していくことができるようになります。
単独親権では子の監護・養育に関する事項をすべて一方の親が決定することになるのに対し、共同親権を選択することで、別居親でも具体的に子の監護・養育に携わっていくことが可能となるといえるでしょう。
(2)養育費が支払われやすくなる
共同親権にすることで、養育費が支払われやすくなるという効果が期待されています。
現行法でも、親である以上は扶養義務を負うため、法的には養育費を支払う義務があるのですが、親権者ではないということで監護・養育に関与できず、親としての責任感もないことから、養育費の取り決めをしていなかったり、支払いをやめたりしているケースが散見されます。
共同親権を選択することで、監護・養育に携わりつつ、親としての責任をもって養育費を支払っていくようになると考えられます。
(3)面会交流が実施されやすくなる
面会交流についても、そもそも離婚時に取り決めが無かったり、初めは実施していたものの徐々に実施されなくなったりするケースが存在します。
他方で、両親と十分な交流の機会を持つことは子の健全な育成にとって重要と考えられており、共同親権により、別居親も親権者として継続的に面会交流を行っていくことが期待されています。
(4)親権争いが避けられる
現行法上は、離婚の際に父母のいずれか一方のみを親権者と定めるしかないため、どちらが親権を獲得するかが熾烈な争いに発展することもあります。
もちろん、親権を獲得したいと考えることは親として当然の心理ですが、子の連れ去りであるとか、親権争いにおける言動等が子を傷つけてしまうといった形で、子にとって望ましくない影響を与えてしまうケースも存在します。
共同親権を選択することでそのような争いを避けることができるというのもひとつのメリットであるといえるでしょう。
5 共同親権のデメリットを解説
(1)親権者間での協議が必要になる
共同親権を選択した場合、主に子に関する重要な事項について、親権者間で協議しながら決定していなかなければなりません。
このことは、同居親の側からすると負担に感じられることも出てくると思われます。
例えば、子の進学先といった事項で意見が対立する場合、協議自体も相応の労力を伴うでしょうし、意見がまとまらない場合、裁判所による決定を求めなければなりません。
(2)DV・モラハラ等の被害から逃れられなくなる
離婚の原因としてDVやモラハラがあるようなケースだと、被害者が加害者とのつながりを断ち切れず、DVやモラハラの被害から逃れにくくなるといったリスクが懸念されています。
なお、DVなどについては、後述のとおり子の利益を害する事情があると認められる場合であれば、単独親権を定めるものとされています。
6 共同親権を獲得するためのポイント
共同親権について、協議が整わず、裁判所が判断する場合、裁判所は、子の利益のため、父母と子の関係、父と母の関係その他の一切の事情を考慮しなければならないものとされています(改正民法819条7項前段)。
加えて、父母のいずれかが子の心身に害悪を及ぼす恐れがあると認められる場合や、父母間で暴力等(暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動)があり共同で親権を行うことが困難な場合など、共同親権にすることが子の利益を害すると認められるときは、一方のみを親権者と定めなければならないものとされています(改正民法819条7項後段)。
そのため、共同親権獲得のためには、子との関係では、当然のことではありますが、身体的・精神的な虐待をしてはならないほか、離婚に関する諍いを子に見せるだとか、配偶者の悪口を子に吹き込むといった形で子に悪影響のある言動は避けるべきでしょう。
加えて、共同親権を行使することが難しい場合には単独親権を定めることになりますので、配偶者との間でも、暴力やモラハラなど、子に関する話し合いが難しくなるような言動は控えるべきです。
これらに注意しつつ、裁判所の手続きにおいては、共同親権の妨げとなるような事情のないことを適切に主張していくことが重要になると考えられます。
7 離婚問題にお悩みの方は当事務所にご相談ください
離婚問題のうち、親権問題は特に重要な問題であり、共同親権について関心のある方も多いと存じます。
改正法の施行が近づいてきておりますので、現在においてはこれも視野に入れた対応を検討する必要があることから、親権問題については法改正にきちんと備えている弁護士事務所に相談いただくことをお勧めいたします。
離婚問題でお悩みでしたら、ぜひ当事務所にご相談いただければと存じます。
(弁護士・神琢磨)